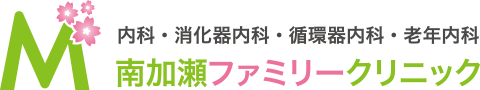無駄な医療??(かぜに抗生剤を処方すること)
「ここ最近、無駄な医療をしている開業医がいる」という記事が目立ちます。
無駄な医療として記載されている代表が、「かぜに対する抗生剤」でしょう。
かぜに抗生剤を処方することがだめである、という意見には反対です。
そのことを中心に記載します。
①風邪とは
正式には、感冒症候群といいます。呼吸器病学会が、専門的にしっかりと解説をしています。
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/a/a-01.html
「一般に鼻腔から喉頭までの気道を上気道といいますが、かぜ症候群は、この部位の急性の炎症による症状を呈する疾患をいいます。時として、この炎症が下気道(気管、気管支、肺)にまで波及していくことがあります。」
上記のように記載されています。つまり、副鼻腔炎、咽頭炎、気管支炎をさします。
症状としては、鼻水(副鼻腔炎)、喉の痛み(咽頭炎)、痰(気管支炎)が主です。
「かぜ症状群の原因微生物は、80~90%がウイルスといわれています。主な原因ウイルスとしては、ライノウイルス、コロナウイルスが多く、RSウイルス、パラインフルエンザウイルス、アデノウイルスなどが続きます。ウイルス以外では、一般細菌、肺炎マイコプラズマ、肺炎クラミドフィラなど特殊な細菌も原因となります。」
原因の大半はウイルス感染であり、このことが抗生剤が要らない、ということに繋がります。
「かぜ症候群は、患者のくしゃみなどで飛散する飛沫を介してウイルスなどの病原体が、気道内に入って気道粘膜に付着し、侵入と増殖することから始まるとされています。発症するかどうかは、環境の要因や感染した人の要因によって決定されます。」
風邪の人がそばにいて、その人からウイルスが飛沫でとび、それが体に入ることで感染します。
風邪をひいている人のそばにいると感染しやすいです。
そのうえで、エアコンにあたったり、栄養がわるいと感染に至ります。
「咽頭ぬぐい液などからウイルスを直接に分離同定するか、もしくは初診時と2週間後位の血液検体を用いて有意な抗体価上昇を認めれば診断できます。しかし、一般的には原因微生物の同定は困難な症例が多く、また、患者の身体所見から診断を下すことも少なくありません。」
診断は、基本的に診察で実施します。
「ウイルス性のかぜ症候群であれば、安静、水分・栄養補給により自然に治癒するためにウイルスに効果のない抗菌薬は不要です。鼻汁を減らす薬、解熱剤などの使用など、いわゆる対症療法を行います。しかし、扁桃に細菌感染を疑わせる分泌物が認められるような場合には、抗菌薬投与が必要になることもあります。」
ウイルス感染故に、抗生剤不要、という流れになります。
②かぜの問題点
「風邪に抗生剤不要」として研究をしているのは主に大学です。
一方で、大学では風邪は診察しません。”風邪ぐらい”で大きな病院には来るな!と言われています。
つまり、風邪の総評をする大学は、風邪を診察しません。
日本中の風邪の大半を開業医が診察しています。
ぼくも、開業してから、初めてかぜ症候群について、しっかり学んだと思います。
診察の経験のない大学病院の医師が「ウイルスが原因だから抗生剤不要」といい、抗生剤を処方する開業医を非難します。
③抗生剤が必要なとき
・扁桃炎→扁桃腺が腫れた場合、溶連菌が関与していることが多いです。
溶連菌が関与している場合には、しっかりと抗生剤投与しないと改善しません。
・副鼻腔炎→抗生剤なしでも改善します。ただし、時間を要します。
抗生剤を服用したほうが罹患日数が短くなる、と言われています。
・肺炎に移行しそうな上気道炎→肺炎に至る可能性があり、抗生剤が必要です。
これ以外にも、経験的に、高熱の場合に抗生剤を処方することがあります。
高熱→インフルエンザ、コロナでもないので解熱剤のみで→熱が全く引かない、というのをよく経験します。
これは、大人は扁桃腺が小さいため、腫脹しているのが見えていない可能性があります。
また、コロナ感染のときに、抗生剤を使ったほうが喉の赤みが早く引いた、と耳鼻科医が報告しています。
ウイルス感染後の続発性の細菌感染をブロックすることで、改善を早める可能性があります。
④実際に
喉の所見により、抗生剤を処方することはあります。
特にコロナを経て軽い風邪の人は来院しなくなったため、風邪で来る人の大半が「日数が経っても治らない」「いつもと違うような風邪症状である」という人であり、結果として抗生剤を処方することが多いです。
また、「はやく治したい」とみんな思っているので、少しでも改善が早まるなら抗生剤を服用したいと思うのは普通だと思っています。
そのため、当院では、抗生剤を処方することが多いです。ただ、診察上で不要と判断したときには、もちろん処方していません。処方する際には理由をお伝えしています。